こんにちは、バラ十字会日本本部の本庄です。

東京板橋では、早くも桜が散り始めています。石神井川の川面や岸が、雪を散らしたように桜の花で飾られています。
いかがお過ごしでしょうか。
ノンフィクションライターとして有名な井沢元彦さんの著書「逆説の世界史」を最近読み、子供のころに学校の歴史で教わったことが、今ではいくつも覆されていることを知りました。
たとえば、もしあなたが私と同じぐらいの年代でしたら、日本で農業が始まったのは弥生時代であり、縄文時代には行なわれていなかったと、学校で教えられたのではないでしょうか。
ところが、青森市に三内丸山遺跡が発見され、縄文時代にもクリ、ゴボウ、マメ、ヒョウタンなどの栽培が盛んに行われていたことが、現在では分かっているそうです。もっと南の地では稲作も行なわれていたそうです。

あるテレビ番組で紹介されていたのですが、アメリカ大陸を最初に発見したヨーロッパ人は、コロンブスではなく、実はバイキングの人たちで、コロンブスより500年も前のことなのだそうです。
歴史については特に、最新の情報を手に入れることを心がけないと、知識が時代遅れになってしまいますね。
先ほどの本には、ピラミッドがファラオ(古代エジプトの王)の墓ではないという話題がありました。このことは、以前からバラ十字会の専門家たちも主張していた事柄です。
正確に言うと、ピラミッドのある場所の地下でファラオのミイラが今後発見される可能性はありますが、この壮大な建築物の地上部が本来作られた目的は、墓として用いられることではありませんでした。
この話は、人はいったん何かを思い込んでしまうとそれに強くとらわれてしまうという、特に教訓的な一例だと私には感じられました。
ピラミッド王墓説の発端は、どうやら、紀元前5世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスらしいのです。ヘロドトスが生きていた時代は、ピラミッドが作られてからすでに2000年以上が経っているのですが、王の墓らしいという当時の人の言い伝えを彼は記録しました。
そしてこの話と、ピラミッドに玄室(棺を納める部屋)と思われるような場所が見つかったということが、その後の歴史家の先入観を作り上げることになります。
そしてそれからは、矛盾があっても、無理につじつまが合わせられるようなことが起こりました。
たとえば、ピラミッドが建設される以前のエジプトでは、遺体は必ず地下に葬られています。ですから、地上の建設物が墓であるという説は、そもそも自然ではないのだそうです。
また、ピラミッドからは、ファラオのミイラや副葬品が発見されたことは一度もありません。しかし、墓泥棒の痕跡がない場合でもそれは盗掘のためだと説明されました。
ある王の時代にピラミッドが2つ作られた例もあります。この場合には、墓が作り直されたのだという理由がつけられました。
最大のピラミッドであるクフ王のピラミッドは、もしこのファラオが即位してから製作されたとすると、製作期間が20年ほどとなるのだそうです。そして、この期間内に完成させるためには、平均2.5トンほどの重さの200万個以上の石を、2分30秒に1個の速さで積んでいかなければならないのだそうです。

ですから、クフ王の墓とされているピラミッドは、このファラオが即位する以前から製作が始められていたのであり、彼の墓であると考えることはできません。
このように、常識が大きく覆されるという話は、歴史上に何度も起こっています。
たとえば、地球が宇宙の中心であるという天動説が世の常識になっていた当時、地球は太陽の周りをまわっているという地動説に賛同したイタリア人、ジョルダーノ・ブルーノは火刑になりました。
古生物の化石から、地球の長い歴史の中で植物も動物も徐々に進化し、形を変えてきたことが立証されますが、現在もそれを認めない人たちがいます。
私たちは、いったん固定的な考え方にとらわれると、なかなかその常識から抜け出すことができず、自分と異なる考えの人を許すことさえできなくなってしまうことがある。このことはほんとうに、決して忘れてはいけないことだと思います。
この機会にぜひ考えていただきたいのです。あなたがとらわれている最大の先入観は何でしょう。それは、どのようにしたら分かるでしょうか。
私も、じっくりと考えてみることにします。
さて、脇にそれてしまいましたので、話を戻しましょう。
それでは、ピラミッドの建設目的は何だと考えられるのでしょう。

古代エジプト研究で有名な早稲田大学の吉村作治博士は、ファラオが再生もしくは復活するための宗教的装置だとしています。
バラ十字国際大学のエジプト学の研究者たちの多くは、当時の神秘学派の人たちが、意識のレベルを上昇させるための式典に使った舞台装置ではないかと考えています。
今後ハイテク装置を使って、ピラミッドの内部がさらに詳しく調査されていくことでしょう。
22世紀の歴史学者はピラミッドについて何を語るでしょうか。古代エジプト人の知識は、私たちに何を教えてくれるでしょうか。
こう考えると、とてもワクワクします。
それでは、また。
追伸:メールマガジン「神秘学が伝える人生を変えるヒント」に、こちらから登録すると、このブログに掲載される記事を、無料で定期購読することができます(いつでも配信解除できます)。
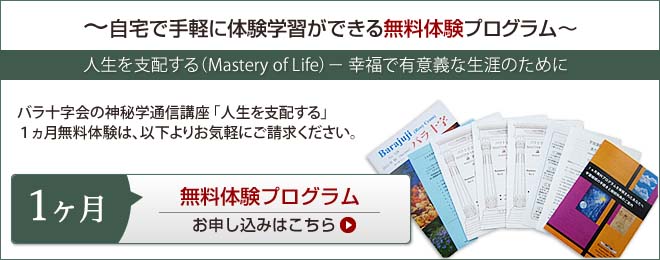








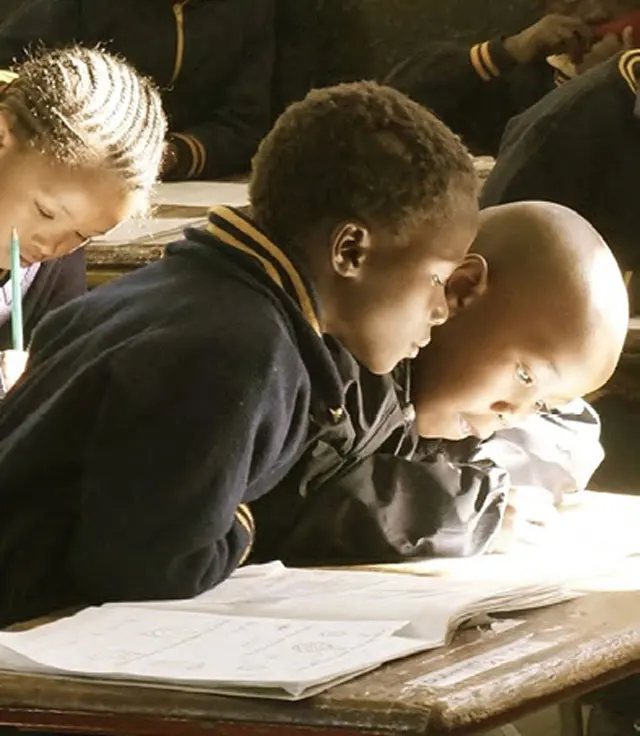

コメントは受け付けていません。