こんにちは。バラ十字会の本庄です。

すっかり秋が深まりましたね。朝晩が寒いぐらいですし、日暮れがずいぶんと早くなりました。
いかがお過ごしでしょうか。
もう半月ほど前のことになりますが、出張でカナダのモントリオールに行っていました。帰りの飛行機が台風19号のために2度も欠航になり、3日も足止めを食らいました。
しかしそのおかげで、モントリオール市内やラシュートという町の森を散策することができました。写真を撮ってきましたので、ご紹介させていただきたいと思います。
さて、「モントリオールは島ですよ」と、地元の人はよく語ってくれます。確かに地図を調べると、モントリオール島と書かれています。セントローレンス川は、アメリカとカナダの国境にあるオンタリオ湖から発して、北東に流れ大西洋に注ぎますが、モントリオール島はこの川の中州(なかす)です。
ただ、中州とは言っても、170万人が住む巨大都市であり、フランス語圏の都市としてはパリに次ぐ世界第二位の人口を誇ります。
かつて、私の能天気な友人が、モントリオールのことを何か田舎町のように勘違いしていて、タクシーの運転手さんにこう言ったことがあります。
友人:「モントリオールのギリシャ料理店を予約したんだけど行ってくれない」
運転手さん:「はぁ? 何軒あると思ってるんですか」
モントリオール島のおおむね中央には、モンロワイヤルという公園があります。そして、美術館、博物館、大学、大きな教会などの観光名所の多くが、この公園の東から南東に集中しています。
公園のすぐ東は、高層ビルが立ち並ぶにぎやかなダウンタウン(商業地区)で、そのさらに東の島の端は、やや静かな感じの旧市街です。
ダウンタウンの中でも最もにぎやかなのは、サント・カトリーヌ通りです。この写真のような感じで、おしゃれなお店が並んでいます。
(写真はクリックすると拡大されます。)


ところで、レナード・コーエンというモントリオール出身のシンガーソングライターをご存知でしょうか。彼は50歳のときに『ハレルヤ』という作品を作詞作曲します。題名からは宗教的な歌を想像してしまうのですが、テーマはそうではありません。
本人が歌っていた時にはそれほどでもなかったのですが、ボブ・ディランやジョン・ケイルがカバーすると大ヒット曲になりました。映画やドラマにも頻繁に使われるようになり、今では英語圏では知らない人がいないほど有名です。
この歌は、旧約聖書に出てくるエピソードを借りて、愛する人との別れの辛さと、厳しい現実への冷めた肯定を歌った美しい詩です。メロディーも素晴らしく、真の名曲だと思います。
彼は2016年11月6日に亡くなったので、没後3年の記念のイベントがもうすぐ行われるとのことでした。生前に彼が住んでいたアパートの壁面には巨大な彼の肖像画が書かれています。

町を歩いていると、世界の女王マリア教会(Basilique-cathédrale Marie Reine du Monde de Montréal)が見えてきました。すごい名前ですね。この教会は、カトリックの総本山であるローマのサンピエトロ大聖堂を、4分の1の大きさにコピーした教会なのだそうです。

内部に入ると、確かに天蓋もサンピエトロ大聖堂に似ています。実は2か月ほど前にローマで仕事があり、サンピエトロ大聖堂を観光する機会があったのです。



台風のせいで、まったく予定していなかった観光をすることができて、今ここにいる。何か不思議な偶然を感じました。
教会の内部は、ドームも美しく、巨大なパイプオルガンが据え付けられており(聴きたい!)、ほんのひととき、深い静けさを感じることができました。

この写真は、レンタサイクルを運ぶトラックです。地元の若い人は、スマートフォンのアプリを用いて、良くレンタサイクルを使うそうです。

歩いていると、奇妙な看板を見つけました。駐停車禁止の警告でしょうが、これほどいいかげんな仕事は見たことがありません。何がいいかげんか? どうぞ写真を見てください。

これはモントリオール国際会議場です。美しい建物ですね。

さてここからは旧市街です。昭和初期のような薄暗い感じのコンクリートで建物が造られていて、懐かしい感じがします。これは、モントリオール最古の銀行だということです。

観光馬車も走っていました。雰囲気のある建物が並び、石畳も素敵です。


これはノートルダム大聖堂です。教会内部がライトアップされ、パイプオルガンを聴くことのできる夜のショーがあるとのことです。長い行列ができていましたので、中に入ることはできませんでした。

これはオールドポート(旧港)です。いまではヨットハーバーになっていて、さびれた感じが魅力的です。

ここには旗が3本掲げられていました。左からカナダの国旗、ケベックの州旗、モントリオールの市旗です。

ケベック州はフランス語圏で文化が特徴的であり、地元の人の話では、数年まではカナダからの独立運動があったのだそうですが、自治権が拡大された結果、現在では落ち着いているとのことです。
以前に、ケベック州旗に用いられているアヤメの意匠(フルール・ド・リス)が付いたガラスのぐい飲みをおみやげに買ったことがあります。しゃれたデザインで、今でも日本酒を冷で飲むときに愛用しています。
しばらく歩くと、ジャック・カルティエ広場に着きました。ジャック・カルティエとは、セントローレンス川に初めてたどり着いたヨーロッパの探検家で、この地をカナダと命名した人です。
彼の名前にちなんだこの広場は観光名所です。多くの観光客がいました。周囲には花で飾られたおしゃれな屋外レストランが並んでいます。
この写真の後ろに見えているのはモントリオール市庁舎です。手前は、似顔絵書きとシャーベットとアイスの屋台です。

ここのアイスは独特で、注文すると、大きな容器にかき氷を敷き詰めたものを持って、お店の人がやってきます。そこに棒アイスに使うような棒を置き、その上からメープル・シロップを垂らすと、シロップが冷えて固まり、手で持つことのできるアイスができあがります。
半月後がハロウィンなので、お花屋さんにはカボチャが飾り付けられていました。

さて、モントリオールから離れましょう。会議のために私が宿泊していた研修施設は、モントリオールから西に50キロほど離れたラシュートという町にあります。
この施設はバラ十字湖(Lac de la Rose-Croix)と美しい森に囲まれています。建物の庭にはブルージェイ(青カケス)やリスがやってきます。

モントリオールや、その周辺の土地のこの時期はインディアン・サマーと呼ばれ、晩秋にもかかわらず、暖かい過ごしやすい日が一週間ほど続きます。紅葉も盛りで、日本からも多くの観光客が訪れます。
しかし、この時期が終わるとラシュートでは、とたんに朝の気温がマイナスにまで下がります。さらに真冬には、雪は1メートルほどしか積もらないのですが、最低気温がマイナス30度にもなり、湖は完全に凍ります。
気温差のため、大きなカエデが美しく色づきます。早朝には、静かに歩いているとシカと出会うこともあります。杉の木の小さな苗が育っていました。杉の木の種を拾ってきて、ベランダの鉢に植えました。
数年前の秋のことですが、会議の合間に森を散策していて、「バシャーン」という音を突然聞いてびっくりしたことがあります。湖に住んでいるビーバーが切り倒した木が湖面をたたいた音でした。
これは写りがあまり良くないのですが、ビーバーの泳いでいる姿です。

今回は、モントリオールとラシュートの様子をご紹介しました。
少しでも楽しんでいただけたなら幸いです。
下記は私の前回の記事です。この記事はローマの町についてのものですが、こちらにも、現地で私が撮った写真を掲載しています。よろしければどうぞ。
参考記事:『古代ローマのバシリカと音楽の聖人』
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
また、お付き合いください。
追伸:メールマガジン「神秘学が伝える人生を変えるヒント」に、こちらから登録すると、このブログに掲載される記事を、無料で定期購読することができます(いつでも配信解除できます)。















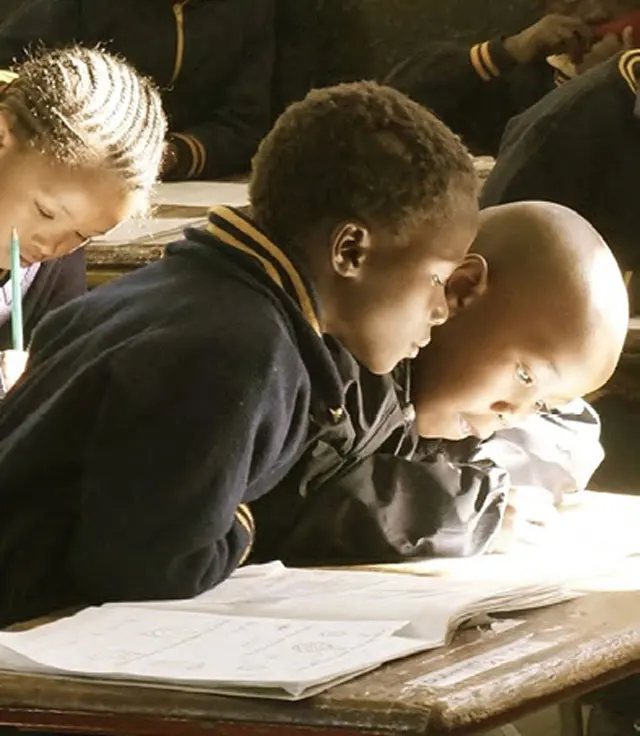

コメントは受け付けていません。