こんにちは。バラ十字会の本庄です。
この数日、東京板橋では雨が降り続いています。
いかがお過ごしでしょうか。台風21号が心配ですね。
さて、聖徳太子の十七条憲法は「和を以て貴しと為す」で始まるそうですが、それ以降の多くの時代に日本では、人と人の「和」ということが、社会で特に大切にされてきたのではないかと思います。
しかし、このことには、ネガティブな側面とポジティブな側面の両方があるのではと、最近、考えていたのです。
ネガティブな側面としては、創造性や起業家精神を押しとどめてしまったり、自由な議論を妨げてしまったりする場合があるということが考えられます。
「出る杭は打たれる」とか、「物言えば唇寒し秋の風」ですね。
一方でポジティブな側面としては、これはまだ考えている最中なので、あまり論理的に説明できないのですが、「和」が社会的な絆、言葉を超えた次元の理解の基礎として働き、それが元になって、繊細な文化が育まれてきたのではないだろうかということです。
このようなことが、最近つらつらと、とりとめもなく頭の中に巡っていたのです。
すると友人から、このブログへの寄稿記事が届いたのです。読んでびっくり! アメリカの作家スタインベックの小説を題材にして、「一つ」、「皆が一緒」という言葉で、この話題がしっかりと取り上げられていました。
メールでこのことを彼に話すと、「シンクロニシティ」ですねと言われました。
今回は、その記事をご紹介させていただきます。
参考記事(前回の寄稿):文芸作品を神秘学的に読み解く(6)『星の王子さま』
▽ ▽ ▽
文芸作品を神秘学的に読み解く(7)
『怒りの葡萄』(The Grapes of Wrath)
ジョン・スタインベック著(John Ernst Steinbeck)

アメリカ人作家ジョン・スタインベックの1939年の作品です。舞台は1930年代のオクラホマ州。ここに住む貧しい農家ジョード家を中心とした物語です。

ジョン・スタインベック ノーベル賞受賞(1962年)当時
By Nobel Foundation [Public domain], via Wikimedia Commons
大砂嵐が起こり大凶作になり、そして地主に地代を払えなくなり、一家は否応なく、果実がたわわに実るとされる「夢のカリフォルニア」へと旅立ちます。そしてやっとの思いでカリフォルニアに着くのですが…
殺人を犯して刑務所に入っていた長男のトム・ジョードが仮出所して実家に向かって旅しているところからこの物語は始まります。
このことからもわかるように主人公一家を始めそれを取り巻く人々も決して清廉な人たちばかりではなく、ときには粗雑さもさらけ出します。作者はそんな一家の生業(なりわい)をしっかりと描写していきます。
さて、神秘学的なポイントを3つ取り上げてみましょう。一つ目は『人に与える』ということについてです。特徴的な2つの場面を見てみましょう。
トムが刑務所から仮出所して帰ってみたら、我が家はなくなっており、食べるものもありません。途中で出会って道連れになった元説教師と二人で途方に暮れてしまいます。
そこへもう一人、男がやってきます。その男は家族がカリフォルニアへ向かった後も、一人残って蛙やネズミを喰って生き延びています。
彼はこの日たまたまウサギを罠で仕留めました。しかし彼は、やっと手にしたこの獲物を二人に分けてやります。
また、家を追い出され一時的に伯父の家に寄宿し、食べ物がなくなってきたジョード一家ですが、ある時、父親が母親に「見知らぬ二人連れが一口何か食べさせてほしいと言っている。どうしようか?」と訊くと、
母親は、気持ちのよい静かで落ち着いた声、親しげに高ぶることのない声で答えます、「入れてやんなさいよ。食べ物はたくさん作ったから」と。
自分も貧しいが、他の人が困っていたら助け合うのは当たり前のこと。この思想は全編を通して貫かれています。
二つ目は『正義』について。次の場面を見てみましょう。
見知らぬトラクターがやってきて、畑を耕し始めます。まだ立ち退かない農家がいれば早く立ち去れと冷たく言い放ちます。大規模農場を作るために地主が送り込んだのです。
トラクターを運転していたのは、やはり小作農だった近所の若者でした。その時のシーンを一部見てみましょう。
農民がトラクターの運転手に言います、「おい、おまえはデービスの息子じゃないか」
運転手は答えます、「そうだよ」
「それなのに何でこんな仕事をやっているんだ? この土地のものに対して」
「一日3ドルになるからさ。俺は妻も子どもも養わなくちゃならない」
「しかし、おまえが一日3ドル稼ぐために、15も20もの家族が路頭に迷うことになるんだ。それは良いことじゃないだろう」
「そんなことは考えてられないね。子どもを養わなくちゃならないからさ」
「そうしたら俺はライフルでもっておまえを追い払ってやるぜ」
「俺にはどうしようもないんだよ。俺を殺しても別の男がトラクターでやってきて、あんたの家をぶっ潰してしまうだろうよ」
「だったら俺は誰を相手にしたら良いんだ?」
「知らないね。相手なんていないんじゃないか。とにかく俺が受けた命令を教えただけだよ」
このトラクターの男の主張や行動は理にかなっているのでしょうか。彼の言っていることに正義はあるのでしょうか。

この2つのポイントが通奏低音のように流れながら物語は進んでいきます。
しかしジョード家の父親は、「このオクラホマの土地は、祖父がインディアンを追い出して自分のものにした。そして父親の俺が開墾したんだ。だからジョード家のものだ」と主張しています。
またカリフォルニアについては別の人がこう述べています。
「カリフォルニアは、元々はスペイン人が住んでいたんだ。後から来たアメリカ人がスペイン人を追い出して奪った土地なんだ。だから今の地主たちは、後からやってくるオクラホマ人たちに盗まれ乗っ取られると思っているんだよ。」
著者はアメリカ社会そして人類全体の潮流をも投影していると言えるでしょう。人間が陥ってしまう、もしくは元々内部に秘めているエゴをもさらけ出します。
そんな中、巨大な歴史のうねりの中でも決して揺るがない「人間性」への信頼が読み取れます。それすらなくなったら私たち人類は崩壊してしまうでしょう。
3つ目は『合一』ということについて。次の場面を見てみましょう。
皆に請われて、元説教師は、「説教師ではなくなったから説教はできない」と言いながら、オクラホマでの最後の食事の祈りを始めます。
いわば最後の晩餐です。実際彼はイエス・キリストを引き合いに出しています。その中で彼はこう言っています。
「~ある時私は疲れ果ててさまよい歩いていた。魂までがすっかり疲れ切っていた。そして、どうにもならないという気持ちで荒野へ出て行った。太陽が昇るのを見て、そして沈むのを見た。」
「時折お祈りもした。そこに丘があり、そこに私がいた。私と丘はもはや別々のものではなかった。一つになっていた。そしてその一つであることが神聖(holy)だった。」
「そして知った。私たちは一つになっている時、神聖なんだ。人類は一つのものになった時、神聖なんだということを。」
「自分勝手なことをやり出したら、それは神聖ではなくなる。でも皆が一緒というのではなく、いうなれば一人が大きな全体(何もかもthe whole shebang)に結びつくということ。これが正しいことで、神聖なんだ。」
重要な点は「皆が一緒になることではない」ということです。「大きな全体につながっていること」こそが神聖であると述べています。この部分は一種の悟りにも近い状態だったのではないでしょうか。
カリフォルニアには着いたけれども赤貧と失意のどん底に落ち込み、櫛の歯が欠けるように家族も減っていくジョード一家。
ついには住んでいた家も洪水に襲われ、娘の「シャロンのバラ」(Rose of Sharon)は子どもを死産してしまいます。
一家は洪水から命からがら逃げ出し、近くにあったみすぼらしい納屋にたどり着きます。そこには見知らぬ瀕死の男とその子どもがいました。
その男は何も口にすることができず、死の影が忍び寄っていました。そしてシャロンのバラはその男を抱き寄せ自分の乳房(ちぶさ)を含ませてあげます。
彼女の指が優しく彼の頭を撫でます。彼女は頭を上げ納屋を見回し、唇を閉じ神秘的な(mysteriously)笑みを浮かべます。
シャロンのバラのこの微笑みは、「生」への揺るぎない希望なのでしょう。
「シャロンのバラ」とはとても象徴的な名前です。キリスト教の聖書の中に出てくる言葉から名付けられたのでしょう。和名はムクゲです。
春一番に咲く花で、「神(創造主)と結ばれ死から命へと甦らしめたもの」を表します。つまり輪廻転生につながります。
また「シャロン」は元来、ヘブライ語で「森」を意味する言葉ということで、キリスト教世界では肥沃な桃源郷を表すようです。まさにこの物語の象徴なのです。

△ △ △
ふたたび本庄です。お楽しみいただけたでしょうか。
上の文章の最後がキリスト教の話題で終わっていましたので、念のため付け加えておきますが、バラ十字会は神秘学(神秘哲学:mysticism)の教育団体であり、あらゆる宗教から独立した立場を保っています。
私は『怒りの葡萄』をまだ読んだことがありません。とても興味を引かれました。あなたはいかがでしたでしょうか。
では、今日はこの辺で。
追伸:メールマガジン「神秘学が伝える人生を変えるヒント」に、こちらから登録すると、このブログに掲載される記事を、無料で定期購読することができます(いつでも配信解除できます)。


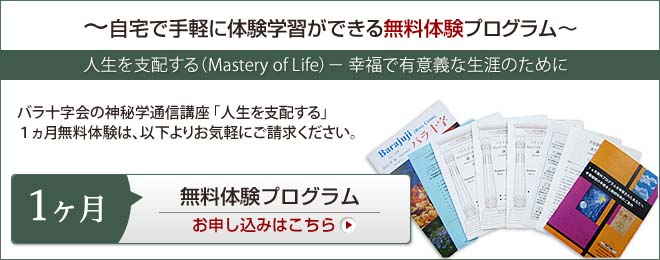








コメントは受け付けていません。