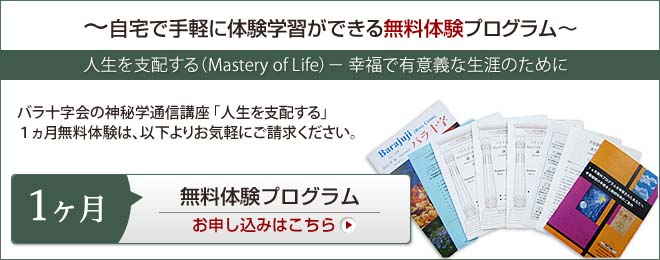こんにちは。バラ十字会の本庄です。
今日は、2023年の小寒と大寒の、ちょうど中間の日にあたります。童謡の「おおさむこさむ」を思い出しました。
私が覚えていた歌詞は「おおさむこさむ、山から小僧が飛んできた」ですが、「おおさむこさむ、山から小僧が泣いてきた」など、いくつかバリエーションがあるようです。
寒い中、いかがお過ごしでしょうか。
札幌で当会のインストラクターを務めている私の友人から、岡本かの子さんの小説についての文章が届きましたので、ご紹介します。
▽ ▽ ▽
『鮨』(すし)ー岡本かの子(著)
文芸作品を神秘学的に読み解く36

この作品は昭和14年(1939年)の1月に発表されました。「富国強兵」、「欲しがりません、勝つまでは」という時代です。家族は家長主体の「家制度」で、食料もどんどん配給制になっていく時です。
主な舞台となっているのは、東京の下町と山の手の境目にある坂や崖の多い街で、繁華街とは真逆の刺激に疲れた人びとが行くような所、閑静な住宅街でも活気あふれる商店街でもない、うらぶれた地域、そこの一番低まった場所にある、「福ずし」という小さな寿司屋です。福ずしは、古い寿司屋を譲り受け、店先だけを作り直し、裏の方は崖に支えられている柱の足を根接ぎして、そのまま住宅として使っています。

主人は東京屈指の寿司店で修行したので、福ずしはそれなりに客が集まるようになっていました。客は十人十色ですが、それぞれが好き勝手、自由気ままにしていることが共通点とも言えます。店の主人もそれを容認しています。
「ともよ」は、父母のやっているこの店の一人娘で、福ずしの看板娘ではあるのですが、仕方なしに店を手伝っています。寿司屋の娘だということを恥ずかしく思っており、女学校時代には、友だちに知られないようにしていました。
また、父母は喧嘩をするわけではないのですが、それぞれが自分のことだけを考えており、そのくせ表面には出さないという家庭です。これらのことがともよを孤独にし、自分とは相容れない客たちを相手にすることで、孤独感を増強させていました。遠足で行った川で泳ぐ魚たちが、来ては去って行くのを見て、自分の店の客たちとオーバーラップさせ、自分はまるで、魚たちが食んでいく杭に付いた苔のようだと思うのでした。

福ずしの客の中に「湊」(みなと)という50歳過ぎのフランス髭を生やした紳士がいます。指には古代エジプトのスカラベの指輪をしています。神秘学を学習している人にはおなじみですが、スカラベは「再生」や「復活」のシンボルです。湊は、店では「先生」と呼ばれ、店主も特別に気使っています。彼は、決まって玉子と海苔巻きで終わるという鮨の食べ方をします。
ともよは湊にある種の好意を抱くようになり、湊もそれに薄々気づいているようです。ある日、表通りに買い物に出たともよは、湊を目にします。彼は観賞用の髑髏(どくろ)魚(ゴースト・フィッシュ)を買ったところでした。ともよは湊に声を掛け、二人で病院の焼け跡の空き地に腰を下ろし、話をするのでした。
「あなた、お鮨、本当にお好きなの」。何を言おうかと逡巡した後、ともよは尋ねました。特別鮨が好きなわけではないという湊が、食べるようになった経緯を語り始めるのでした。
それは玉子と浅草海苔しか食べられなかった湊の子ども時代のことでした。他には時々、生梅や橘(たちばな)の実といった酸味のあるものを囓(かじ)る程度という極端な偏食でした。そんな湊少年を父親は見捨ててしまったようだし、母親については、今いる生みの親とは別に「お母さん」がどこかにいると湊少年は思っていました。彼も孤独の中に生きていたのでした。
そんな中、母親はどうにかして普通に食事をさせようと、鮨を握って食べさせるのでした。はじめは玉子鮨を食べさせました。いつも食べている玉子と酸っぱいものを組み合わせたのが鮨だったのでしょう。次は、母親が「白い玉子焼きだと思って食べればいい」という烏賊(いか)の鮨でした。「象牙のような滑らかさがあって、生餅(きもち)より、よっぽど歯切れがよく」、思いのほか旨かったのです。それから湊少年は母の握る鮨を食べ続け、幻想の「お母さん」とこの母親は同一なのかも知れないと思うようになっていきました。これをきっかけに、食も太くなり、立派に育ったのです。それと相対するように湊家は没落し、父母も兄姉も相次いで他界し、2人目の妻も死に、それからは1人で暮らしているのです。
「ああ判った。それで先生は鮨がお好きなのね」、ともよは言いますが、「いや、大人になってからは、そんなに好きでもなくなったのだが、近頃、年をとったせいか、しきりに母親のことを想い出すのでね。鮨までなつかしくなるんだよ」と湊は答えます。湊は鮨そのものが好きだったわけではなく、母を思ってのことなのだということをともよは知らされます。
そんな長い一人語りを終え、湊は、髑髏魚をともよに与え、去って行きます。

その後、湊は福ずしに全く現れることはなくなり、ともよは湊を見つけようとするのですが、叶わず、涙することさえありました。やがて、ともよも湊のことを気に掛けることはなくなり、「先生は、何処かへ越して、また何処かの鮨屋へ行ってらっしゃるのだろう──鮨屋は何処(どこ)にでもあるんだもの──」と考えるようになったのでした。それは、福ずしの鮨を好んでいたわけでもなく、ましてや自分に会えるからでもなかったということをともよは受け入れていくことになるのです。
疎外感に満ちた人生を送っているともよには、湊は共感を持てる唯一の存在だったのでしょう。そして、湊にとってともよは、これまでの自分を見るようなものだったのでしょう。しかし、孤独に生きてきた湊には、心を通わせるような存在はもう受け入れることは出来なくなっていたのです。
湊との出会いと別れを経験し、ともよは一つ大人になったことで、より強く生きていくことでしょう。
ここで一つ考慮しなければならないことは、湊が自分の過去をさらけ出したから、もう福ずしへは行かなくなったとは言えないということです。人はどうしても短絡的にそういう因果律を見いだしたがりますが、ここに時間の矢は当てはまらないでしょう。手掛かりは、二人がカフェに入るでもなく、崖端にある病院の焼け跡の空地に座り込むということ。これは滅びの心的情景を思い起こさせます。さらには、湊が髑髏魚を買っていたということです。これは読者に「死」をイメージさせます。つまり、会えなくなる最後にともよと二人だけで話すことが出来たということです。そして髑髏魚はともよの手に委ねられます。
こうしてみると、湊は作者である岡本かの子の投映で、ともよは息子、岡本太郎への投げかけなのかも知れません。
この作品を1月に発表したかの子は、翌2月17日に亡くなります。そして、日本は大戦へ突き進んでいきます。寿司屋もネタが入らず休業や廃業に追い込まれた所が少なくなかったようです。そんな中、太郎は芸術家として大成していきます。

△ △ △
再び本庄です。
私はこの小説を知りませんでした。青空文庫で見つけ、読み始めるとすぐに、著者の世界にすっと引き込まれました。
下記は森さんの前回の文章です。
では、今日はこのあたりで。 また、お付き合いください。
体験教材を無料で進呈中!
バラ十字会の神秘学通信講座を
1ヵ月間体験できます
無料で届く3冊の教本には以下の内容が含まれています

第1号:内面の進歩を加速する神秘学とは、人生の神秘を実感する5つの実習
第2号:人間にある2つの性質とバラ十字の象徴、あなたに伝えられる知識はどのように蓄積されたか
第3号:学習の4つの課程とその詳細な内容、古代の神秘学派、当会の研究陣について