以下の記事は、バラ十字会日本本部の季刊雑誌『バラのこころ』の記事を、インターネット上に再掲載したものです。
※ バラ十字会は、宗教や政治のいかなる組織からも独立した歴史ある会員制の哲学団体です。
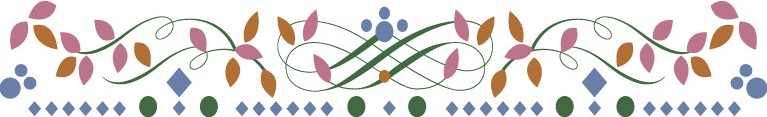
絶対なるものを知ることは可能か
Can We Know the Absolute?
セシル・A・プール
by Cecil A. Poole

絶対(absolute)という概念は、すべてが備わっていること、つまり欠けているものがないことを意味しており、相対という概念の正反対にあたります。相対的なものは対象となるものであり変化するものですが、絶対的なものはそれ自体で完結しており、完璧な状態にあります。絶対なるもの(Absolute)という語は、しばしば、神あるいは神の精神の同義語として用いられます。形而上学(metaphysics)とは何かという問いに対して、それは究極の実在、すなわち究極の存在の理解を目指す学問であるという答えが、あらゆる時代に述べられてきました。この意味で形而上学は、絶対的なものと直接関連しています。
プラトンのイデア説(idealism)を思い起こしましょう。プラトンはイデア(訳注)のことを、物質世界のいかなる物よりも実際のものである(real)と考えました。人間の精神の中に存在する観念(訳注)は、物質の世界をよく映し出していますが、究極の観念、すなわち絶対的なイデア(absolute form)が、すべての個々の観念の上位に存在し、それらを支配しているとプラトンは考えました。こうした考え方に基づいて、イデアは、いかなる物体よりも、より真の実在であるということを、プラトンは自身の哲学の根本原理に据えました。イデアは物質ではなく存在の本質であり、それこそが基礎であり、この基礎によって、物質世界の様々なもの同士を区別することができます。
(訳注:観念(英語:idea)とイデア(英語:form or idea、ギリシャ語:idein):観念とは思考の対象となる意識の内容。幾何学の三角形を例にとると、三角形の観念とは、個々の三角形ではなく三角形全般に対応する意識の内容である。人間は、太さのない三本の線から構成される完全な三角形などというものを一度も見たことがないのに、なぜそれを完全に理解できるのかということが古代ギリシャ哲学で問題になった。これに対してプラトンは、三角形の観念に対応するイデアや、さらには、美、正義、生物種などに対応するイデアが、感覚を超越した世界に実在し、感覚でとらえられる世界(物質世界)を規定しているのであり、人間は超感覚的世界を生前に体験しており、それを想起しているのだと考えた。)
プラトンのこの考え方をより深く理解するために、例を挙げてご説明しましょう。たとえばゾウという動物も人間も、素材という点ではあまり違いはありません。どちらも、同じような物質で構成されています。より専門的に言えば、ほぼ同じ化学的組成をしています。どちらの体の化学物質も、同じような働きをします。しかし一方でゾウと人間には、物質の組み合わされ方にかなりの違いがあります。外見も違えば、動作にも違いがありますし、習性も異なります。しかし、いくつかの類似点もあります。どちらも呼吸をし、血液が体内を循環し、私たちが生命と呼んでいるものを宿しています。

したがって、物質的な対象の間に違いを生じさせているのは、それを構成している物質ではなく、そのイデアなのです。そのため、観念論(訳注)を唱える哲学者は、現実世界はイデアという観点から考察したときにだけ理解できるのであり、私たちの身体の感覚器官を通して知覚した結果の違いから理解できるのではないと主張しており、イデアこそが究極の実在であり、イデアを超越することはできず、このイデアが精神や意識の中に展開するのだという考えを保持しています。これは、イデア以外のすべてのものが幻想であるということではなく、イデアが根本であり基礎であるということを意味します。
(訳注:観念論(idealism):世界の根源が物質ではなく、心もしくはイデアであるという考え方。)
ここで指摘しておくべきことは、一口に観念論と言っても、この形而上学的な立場には分派、つまりさまざまな主義主張があるということです。形而上学は一枚岩ではなく、多くの学派が存在します。
主観的観念論は、存在するのは観念だけで、それ以外のものは存在しないと考えています。イギリスの哲学者ジョージ・バークリー(George Berkeley、1685-1753)は、この説を極端な形にまで展開し、人が知覚する外界というものは一切存在しないという説を唱えました。あるのはただ観念だけであって、人はそれを周囲に投影することによって、物質的な世界が存在すると信じ込んでいるのだと彼は考えました。バークリーの考え方は、ここで行った短い説明よりもはるかに深遠なものです。しかし、主観的観念論とは、観念だけが存在すると考え、それ以外には何もないとする考え方であるという概略はお分かりいただけたことでしょう。
これとは別に、客観的観念論と呼ばれる形而上学の立場を支持する思想家もいます。彼らの考えによれば、宇宙は物質的なものから構成されています。そして、私たちは物質的な物を知覚し、その知覚の結果として、物、物の性質、物の外観、物の働きに関する観念を作り上げます。客観的観念論を信奉する人の考えでは、物質世界は、知覚する人の心の中に観念を誘発する一種の引き金の役割を果たしていることになります。しかし結局のところ、観念こそが現実です。
一冊の「本」を見ているとします。それは紙を、あるやり方で綴じたもののようです。見ているだけでは、「本」というものを事前に知っていない限り、その目的も内容も存在理由も分かりません。しかし、よく調べていくと、それが実は何なのかという観念が意識の中に作られます。本についての印象が得られると、そこから本とは何かという自分の結論が作られ、本の観念が心にとって身近なものになります。プラトンによれば、人間の心の中にある本の観念は、物質の世界で作られたいかなる本よりも完璧な、イデアの代理としての役割を果たしています。

外界としての世界が存在しているということを、多くの人が自明だと考えています。客観的観念論は、外界が存在すると唱えているので筋の通った説であると見なされ、形而上学を研究している多くの人がこの立場を支持しています。私たちは自分が知覚したものしか知ることができません。また、体験し理解できるのは、自分の心の中にある観念だけです。しかし、大部分の人と、そしてその行動から判断されるようにあらゆる動物が、実際のところ、自分の外側に、物質の世界が実際に存在していると見なしているように思われます。ですから、外界という物質世界が存在すると主張することには、もっともな理由があるのを否定することはできません。たとえば私たちは、空いていないドアをすり抜けることができません。私たちはそれが固い物質であることを知っています。したがって、ドアが心の中以外には存在しないという極端な観念論(主観的観念論)を受け入れるのは難しいことです。物質世界が存在するということについては、客観的観念論を信奉する人も唯物論を信奉する人も、考えは同じです。しかし、客観的観念論者である私は、世界は存在するけれども、それは、知覚の結果として生じた、自身の心の中にある精神の解釈や判断に過ぎないと考えています。
いくつかの定義に関する専門的な相違はありますが、事物の認識には2つのはっきりと異なる方法があるという見解で、哲学者、特に観念論を信奉する哲学者は意見が一致しています。第一の方法は、対象の事物を外部から、つまり周囲から認識するというものです。第二の方法は、対象の中に入り込んで認識するというものです。
第一の認識の方法では、対象を知覚するときにどのような視点から見るかということと、その知覚が心の中に作り出したものについて表現するときに用いる記号によって、結果に違いが生じます。私たちは、言葉が、一種の記号に過ぎないことを絶えず心得ておかなければなりません。私たちが表現に用いる言葉は、私たちが理解したり知覚したりしたもののための記号なのです。それに対して第二の認識の方法は、視点や対象物の位置に左右されることはありません。また、いかなる記号にも頼る必要がありません。
第一の方法では、対象を外部から身近な環境の一部として知覚します。こうした知覚の方法は、相対的であると言えます。第二の認識の方法では、対象物の内側に入り込んで知覚することになります。そうすることで、私たちは絶対的なものを手に入れます。
たとえば、空間内にある一つの物体を知覚するとき、物体がどう動いて見えるかは、自分の位置や視点によって変化します。物体が動いているのかもしれませんし、私が動いているのかもしれません。どのように理解するかは、それを対象としてどのように知覚したかと、その知覚を精神がどのように解釈したかに左右されます。しかしもし、その物体が絶対的に運動していると考えるなら、その動いている物体に、ある種の内的状態、つまりある種の精神が備わっていると見なしていることになります。これは、その物体の状態に、自分自身の精神が共感、すなわち調和していることを示しています。対象への共感的な理解、あるいは対象へ自分を投影したか、あるいは自分を対象に投影した結果として、対象の中に自分を没入させていると言えるかもしれません。この第二の認識の方法によって、私は対象の内側にいるのです。このような認識の経験は、私の立場にも、私がその動きを解釈して用いる記号にも左右されません。私はその内部に入り込み、絶対的なものを手に入れています。
もう一つの例として、演劇や映画やテレビドラマに出演している俳優のことを考えてみましょう。ドラマの登場人物のキャラクターを設定したのは作家です。俳優の言動は、作家の決定に従っています。自分の外部にある対象として演技を鑑賞している場合には、その知覚を通して、その俳優と自分を一体化することはできません。一方で、もし自分をその登場人物と一体化させると、その登場人物の存在全体が私の存在となり、彼の行動は私の行動になります。私が演劇や映画を単に観賞している場合は、すべての俳優について私が知ることは、私が演技を観察する視点の結果として生じることになります。

また、演技をしている俳優の特徴はすべて、私がすでに知っている他の人物や事物との比較によってしか知ることができません。しかもそれは、演技の際の身振りやせりふなど、象徴的な記号によって表されます。それゆえに、視点と記号によって、私は自分が目撃している登場人物すべての外側に位置することになります。そのため、その登場人物について私が知ることができるのは、他の人も知ることができるような共通の特徴であり、俳優自身が本当はどのような人であるのかを知ることはできません。その俳優個人に固有であるものとは、その人の自己の本質のすべてにあたります。
そのような本質は、外から知覚したり、言葉や他の記号で表現したりすることはできません。その俳優を目の前で見たときに私に残るものは、その人に関する相対的な概念に過ぎません。それに対して、目の前にいる他の人と私が一つになる、つまり一致するなら、目の前にいるその人が本当は誰なのかについて、私は絶対的かつ完全な認識を得ることになります。この場合、「絶対」は「完全」と同じ意味になります。
また別の例を挙げれば、ある町や都市を、航空写真も含めあらゆる視点から撮影した写真があるとします。しかし、それらを組み合わせても、その町そのものになることは決してありません。実際の町は、自分の足で歩き回って、そのありさまを直接観察することができます。一連の写真は、その町の代理となる相対的なもの(relative representation)に過ぎません。
さらに、この考え方は、詩を翻訳する場合にも当てはまります。一編の詩をありったけの言葉を用いて翻訳し、あらゆる意味の組み合わせを付け加え、原詩にますます忠実な翻訳を得ようとして推敲を施したとしても、それでも訳詩というものは相対的なものです。原詩に含まれている完全な意味、つまり絶対的な意味を再現することは決してできません。ある言語から別の言語へと翻訳を試みたことのある人なら誰でも、原作に含まれている絶対的な意味を表現することがいかに困難であるかを知っています。絶対的なものは、原詩や対象であって、その代わりとなる訳詩や表象(訳注)ではありません。原作であって翻訳でないものは、そもそも完全にそれ自体であるという意味で完全です。それは絶対的なものであり、相対的なものではありません。
(訳注:表象(representation):知覚や記憶や想像によって意識に現れる、その対象の代理となる像。)
同様の考え方を紹介する際に、次のような説明がよくなされます。あなたが腕を上げるとき、その動きはあなたの内部から果たされます。あなたにとって、この動きはごく単純に知覚できることで、特別な思考や分析を必要としません。しかし、私にとってその動きや動作は、私の知覚器官を通してあなたの外側から観察されるものであり、あなたの腕が、空間のある場所を通過し、次に別の場所を通過しているように見えます。この2つの場所の間には、さらにいくつもの場所が存在します。その数を数え始めたら際限がありません。

内側から見れば、絶対的なものは単純です。しかし外側から見ると、絶対なるものを表現するための記号やシンボルが関わってくることで、認識のプロセスは複雑で際限のないものになります。ひとことで言えば、絶対的なものは直観によってだけ理解され、私たちが知覚するそれ以外のものは、分析の範囲内に限定されると結論づけることができます。
この考え方は、フランスの哲学者アンリ・ベルクソン(Henri-Louis Bergson、1859-1941)の次の言葉によく表れています。
「絶対的なものは直観の中にしか存在することができず、それ以外はすべて分析の領分に属する。直観とは、ある種の知的な共感を意味する。直観によって人は対象の内部に入り込み、そこにある固有のもの、したがって表現不可能なものと一体となる。これとは反対に、分析とは操作である。分析は対象を既知のさまざまな要素に還元する。つまり、その対象とそれ以外の対象の両方に共通するさまざまな要素に還元する。したがって分析とは、ある事物を、それ以外の事物との関係として表現することである。」
結局のところ、分析とはすべて翻訳、つまり記号化を進めていくことなのです。代理となるもの(representation)は、類似点が見つかるようなさまざまな視点から選ばれます。直観は、五感による知覚とは対照的に、心の奥深くで起こるプロセスであり、その源は、ソウル(soul:魂)つまり内なる自己の中にあります。バラ十字会の哲学では、直観は、肉体の感覚とは別の経路を通じて知覚する能力であると説明されています。したがって直観は、ある種の感情的なパターンを持つ知的共感であり、直観によって人は自分の外部にある何かと同調することができ、その事物の中にある固有のものと一体化することで、その結果として、その事物についての絶対的な知識を得ることができます。
直観による認識のプロセスは、多かれ少なかれ自然に発生します。それは心の奥深くで起こるため、客観的な分析を試みても、なかなかうまくは行きません。したがって、直観的な体験で何が起こったのかを言葉で表現することは困難です。直観を体験することで、私たちは絶対的なものに近づきます。繰り返し述べているように、絶対的なものは、いかなる種類の記号を用いても説明することができません。
すでに述べたように、絶対的なものは単純で完全です。同様に、直観もまた単純で完全なプロセスです。直観に由来するものは、知覚するいかなるものよりも、絶対的なものに対するあるレベルの理解をもたらす強い傾向があります。これに対して分析は、ある対象を既に知っているさまざまな要素に還元し、その対象とは異なる何かに関連づけて表す操作です。繰り返しますが、分析とは翻訳であり、記号を用いた解釈の展開であり、一連の視点から代理となるものを選ぶことなのです。分析は、外部にある対象について知りたいと強く願ったとしても、決して完全にはならない代理を完成させようと、際限なく視点の数を増やすことになりかねません。
分析のプロセスは無限に続きます。なぜなら、集まるデータは常に増え続け、分析のプロセスは、ますます複雑になっていくからです。しかし、直観という単純な行為は、分析よりも明快です。直観はそれ自体で完結しており、直観によって絶対的なものを即座に把握することができます。さまざまな視点から行われる分析だけでは、絶対的なものを把握することはできません。科学の持つ機能は分析であり、それは主に記号を用いて、対象の世界を、観察した人が知覚した結果として記述しようとすることです。形而上学者が機械論的または唯物論的と呼ぶ立場がありますが、この立場を受け入れている人たちは、自分たちが究極の実在を扱っていると思い込んでいます。
現実の姿をただ相対的に知るのではなく完全な姿で手にする、すなわちそれを完全に把握する唯一の方法、つまり、現実世界の活動を外側から観察するのではなく内部に入り込んでその原因を捉える唯一の方法、分析を行うのではなく直観が伝えてくれるものを体験し心に抱く唯一の方法は、ひとことで言えば、表現や解釈、記号による代理に頼ることなしに現実を直接掴むことです。このことを、形而上学の究極の目標のひとつと見なすことができます。
ベルクソンによれば、形而上学とは、突き詰めれば「記号を使わないことを主張する科学」です。記号を使わないということは、分析を使わないということです。分析を使わないということは、すべてのものの核心に直接迫り、対象の内部に入り込み、客観的な認識ではなく直観を通して学ぶことです。それこそが究極の実在の把握へと向かう真の道であり、形而上学の意図にあたります。
体験教材を無料で進呈中!
バラ十字会の神秘学通信講座を
1ヵ月間体験できます
無料で届く3冊の教本には以下の内容が含まれています

第1号:内面の進歩を加速する神秘学とは、人生の神秘を実感する5つの実習
第2号:人間にある2つの性質とバラ十字の象徴、あなたに伝えられる知識はどのように蓄積されたか
第3号:学習の4つの課程とその詳細な内容、古代の神秘学派、当会の研究陣について









